「振替加算」という言葉を聞いたことがありますか?
年金に関する制度のひとつですが、実はあまり知られていません。
今回は「自分に振替加算がつくのか?」「つくなら、いくらもらえるのか?」
という疑問にやさしくお答えします。
振替加算ってなに?
振替加算とは、加給年金が終了した際に、一定の要件を満たすと
老齢基礎年金に加算される仕組みです。(日本年金機構より)
振替加算の対象者
対象となるのは、以下のすべての条件を満たす方です。
・自分の厚生年金・共済年金の加入期間が240月(20年)未満
・配偶者の加入期間が240月以上
・昭和41年4月1日以前に生まれていること
いくらもらえる?
振替加算の金額は、生まれた年によって変わります。
例えば、大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれまでの方は
年間238,600円支給されます。
それ以降の生まれ年になるほど、段階的に金額は下がり、
昭和41年4月2日以降に生まれた方は対象外となります。
詳しい金額は日本年金機構のホームページで確認してください。
加給年金との違いは?
いつからいつまでもらえる?
基本は65歳以降生涯加算
ただし、配偶者より年上の場合は
配偶者が65歳になった時点からになります。
離婚した場合
離婚後、年金分割の手続きをした場合、
分割された厚生年金の月数と自身の厚生年金の月数の合計が
240月以上になった場合は停止されます。
どんな手続きが必要?
手続き不要
ご自身が65歳になって、基礎年金を受給するようになると
自動的に加算されます。
手続きが必要になる場合がある
配偶者より年上の場合は手続きが必要になります。
現在はマイナンバーを請求書に記入することにより、
戸籍、住民票、所得証明の添付は不要となります。
年金事務所で手続きします。
よくある誤解
・振替加算は配偶者が亡くなられたとしても、停止にはなりません。
・老齢基礎年金を65歳以降に繰下げると、その間は年金の受給自体が始まらないため、
振替加算も支給されません。
また、振替加算は繰下げしても金額が増えることはありません。
・老齢基礎年金を繰上げ請求された場合であっても、振替加算がつくのは65歳以降です。
私の両親の場合
父も母も厚生年金が20年以上ありますので、どちらにも振替加算はつきません。
しかし、母の厚生年金は確か、240ヶ月を数ヶ月越したくらいだったと思います。
例えば、母が厚生年金にあと数ヶ月加入せずに240月未満で止めていたとしたら、
年間約15万円の振替加算を受け取れた可能性があります。
まとめ
・厚生年金の加入月数が240月未満かどうかがポイント(例外あり)
・金額は年齢により異なるが、最大で年間238,600円(令和7年度)
・65歳以降、自動的に支給されるが、配偶者が年下の場合は手続きが必要
・昭和41年4月2日以降に生まれた方は対象外
おまけ
なぜ、昭和41年4月2日以降に生まれた方はが対象外なの?
振替加算は、老齢基礎年金を補うために作られた制度です。
もともと、専業主婦などの「サラリーマンの扶養に入っている配偶者」は、国民年金の加入が任意でした。
しかし、昭和61年4月1日から「国民年金第3号被保険者制度」がスタートし、会社員や公務員の扶養に入っている配偶者も自動的に国民年金に加入できるようになりました。
この制度が始まった昭和61年4月1日時点で、ちょうど20歳になるのが昭和41年4月2日生まれの方です。
この方たちは20歳以降、ずっと第3号被保険者として国民年金に加入できる環境が整っているため、老齢基礎年金の保障が確保されており、あらためて振替加算で補う必要がないと考えられています。
そのため、昭和41年4月2日以降に生まれた方は振替加算の対象外となっています。
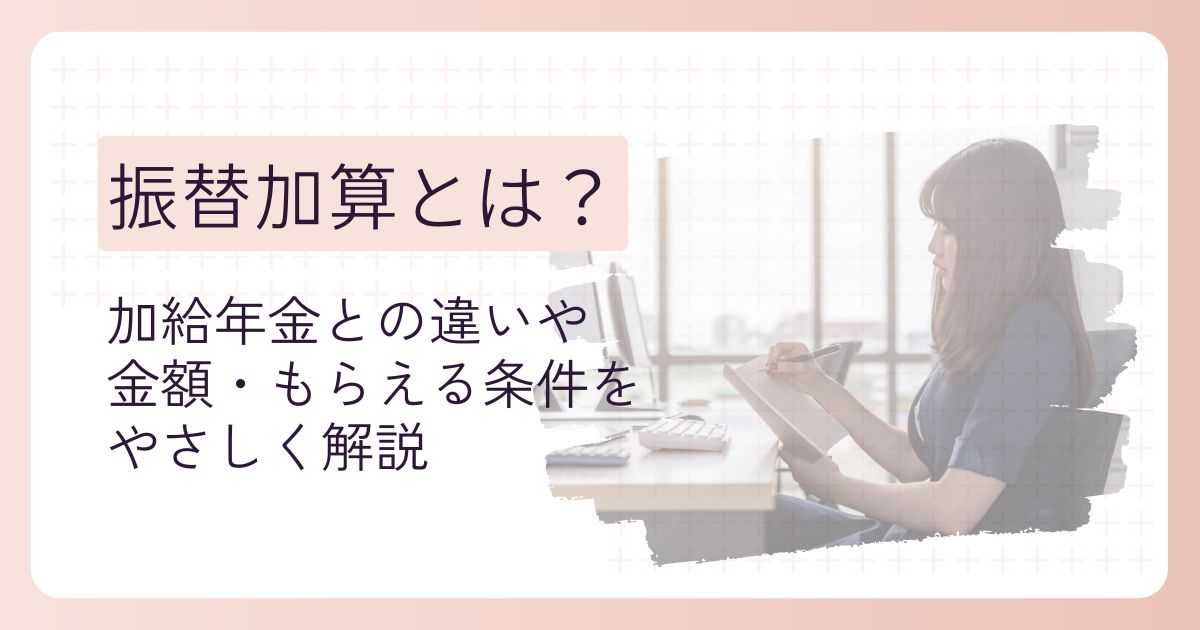
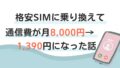

コメント