はじめに
「第3号被保険者」という言葉、なんとなく知っているけど、ちゃんと説明できる人は少ないのではないでしょうか。
今回は、第3号の仕組みや将来の年金額、注意点までわかりやすく解説します!
第3号被保険者とは?
・国民年金の加入者の一種
・保険料は自分で払わず、配偶者が加入している年金制度が負担
・実質的には「保険料負担ゼロで年金がもらえる」という制度
補足
被保険者の種類は、第一号被保険者から第3号被保険者までの三種類です。
第1号被保険者は、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、
農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等
に加入しておらず、第3号被保険者でない方)です。
そして第2号被保険者は厚生年金保険や共済組合等に加入している
会社員や公務員の方をいいます。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満
(60歳以上の方や障がいをお持ちの方は180万円未満)の20歳以上60歳未満の方ですが、
年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、
厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、
第3号被保険者には該当しません。
メリットとしくみ
・保険料の自己負担なし。
・将来、老齢基礎年金がもらえる(40年加入で満額)。
・配偶者勤務する事業所が手続きをするので、自分で手続きをする必要はない。
第3号のままでいい?よくある誤解と注意点
・「保険料払ってないから年金もらえない?」→ もらえます(ただし基礎年金のみ)。
・「保険料は配偶者が支払っている?」→配偶者が加入している年金制度が負担しています。
・「働きすぎると扶養から外れるってほんと?」→ ダブルワークなどで、
厚生年金に加入していなくても、年収130万円超(60歳以上や障がいをお持ちの方は
180万円)で第1号に変わる可能性あり
・「厚生年金に入ったほうが得?」→ 厚生年金に入ると将来、基礎年金+報酬比例部分
が受給できるけれど、保険料負担により手取りは減ります。
得か損かは考え方次第
・「将来第3号は廃止される?」→ 廃止議論はあるが現時点では未定
・配偶者が厚生年金に加入している間はずっと3号のまま?→配偶者が65歳になり
第2号被保険者でなくなった場合は、第1号被保険者となります。
・親の扶養になっている場合は第3号被保険者になれる?→なれません。
第3号被保険者制度は夫婦間のみの制度です。
・第3号被保険者は付加保険料(月額400円)を掛けることはできる?→
国民年金保険料を納付していませんので、付加保険料のみを支払うことはできません。
将来もらえる年金はいくら?
20歳から60歳までずっと第3号被保険者だった場合、
老齢基礎年金として**満額831,700円(令和7年度)**が受け取れます。
また。条件により以下も加算される可能性があります。
・加給年金(配偶者に加算)
・振替加算(自分に加算)
加給年金や振替加算については過去の記事をご覧ください。
おまけ:健康保険の「130万円の壁」とは?
健康保険の扶養に入るための年収基準額は
・一般の方:130万円未満
・60歳以上または障がいをお持ちの方:180万円未満
過去一年間の金額で判断するのではなく、今後一年間の予定収入です。
含まれる収入
・給与収入
・年金収入(遺族年金や障害年金、個人年金など)
・事業・不動産・投資収入
・仕送り
・失業給付
・傷病手当金、出産手当金
・年金生活者支援給付金 など
含まれない収入
・出産一時金など継続しない一時金的な給付
まとめ
・第3号被保険者は保険料ゼロで国民年金に加入できる制度
・ただし、扶養の条件や働き方によって変動する可能性あり
・自分の将来設計に合わせた見直しが大切
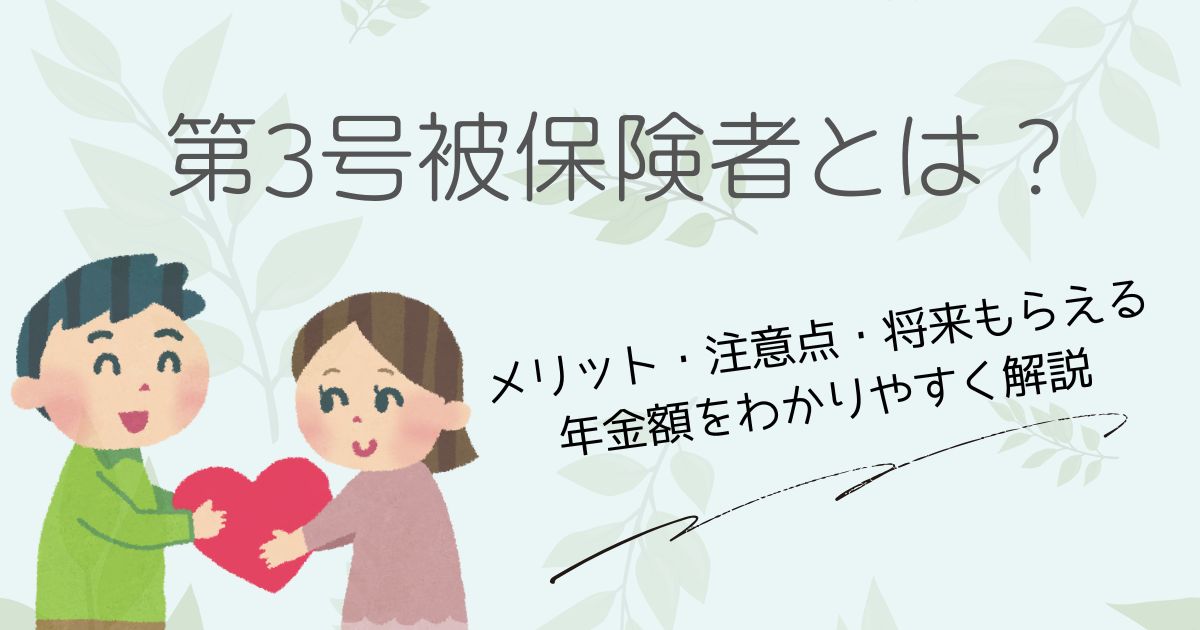
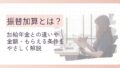
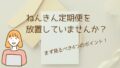
コメント